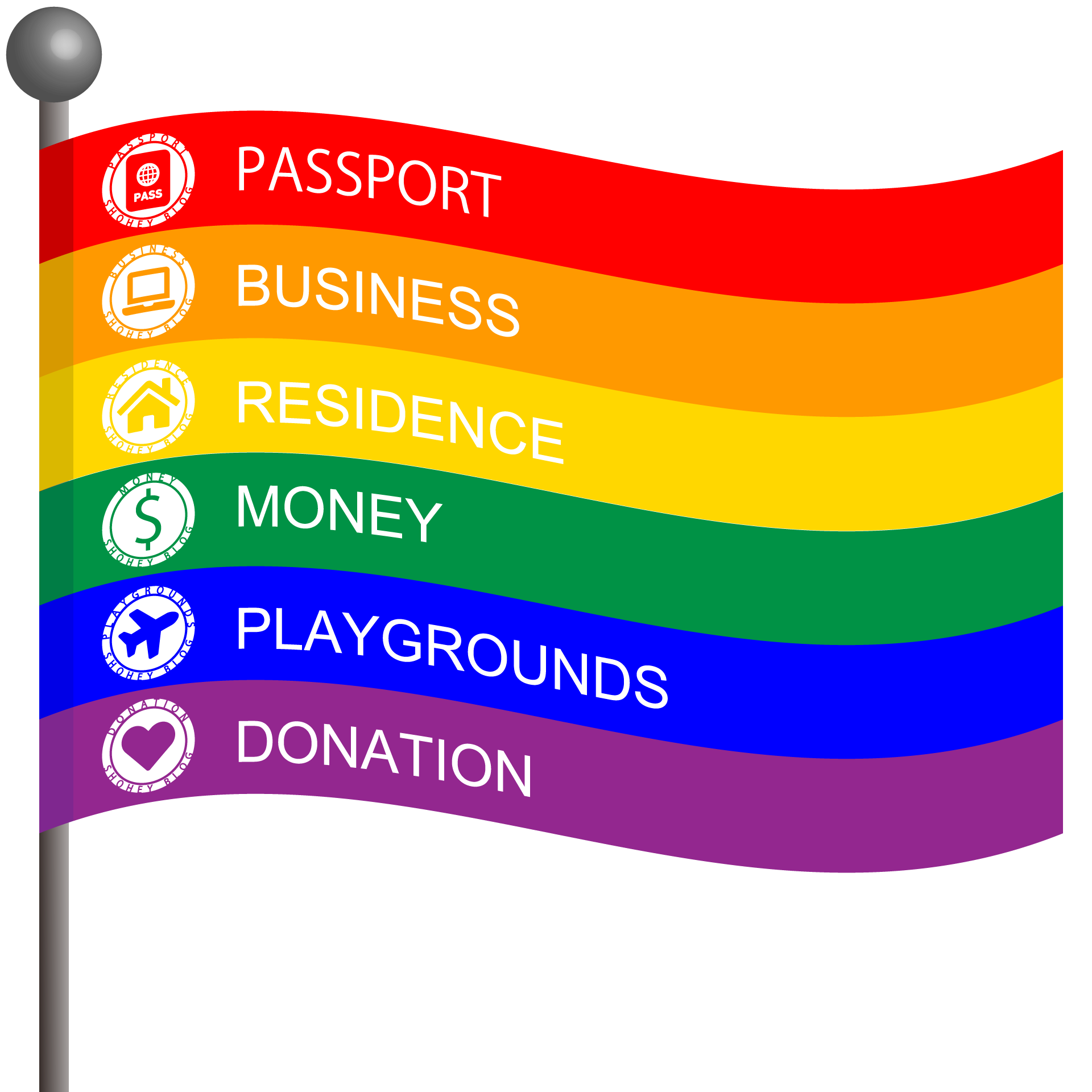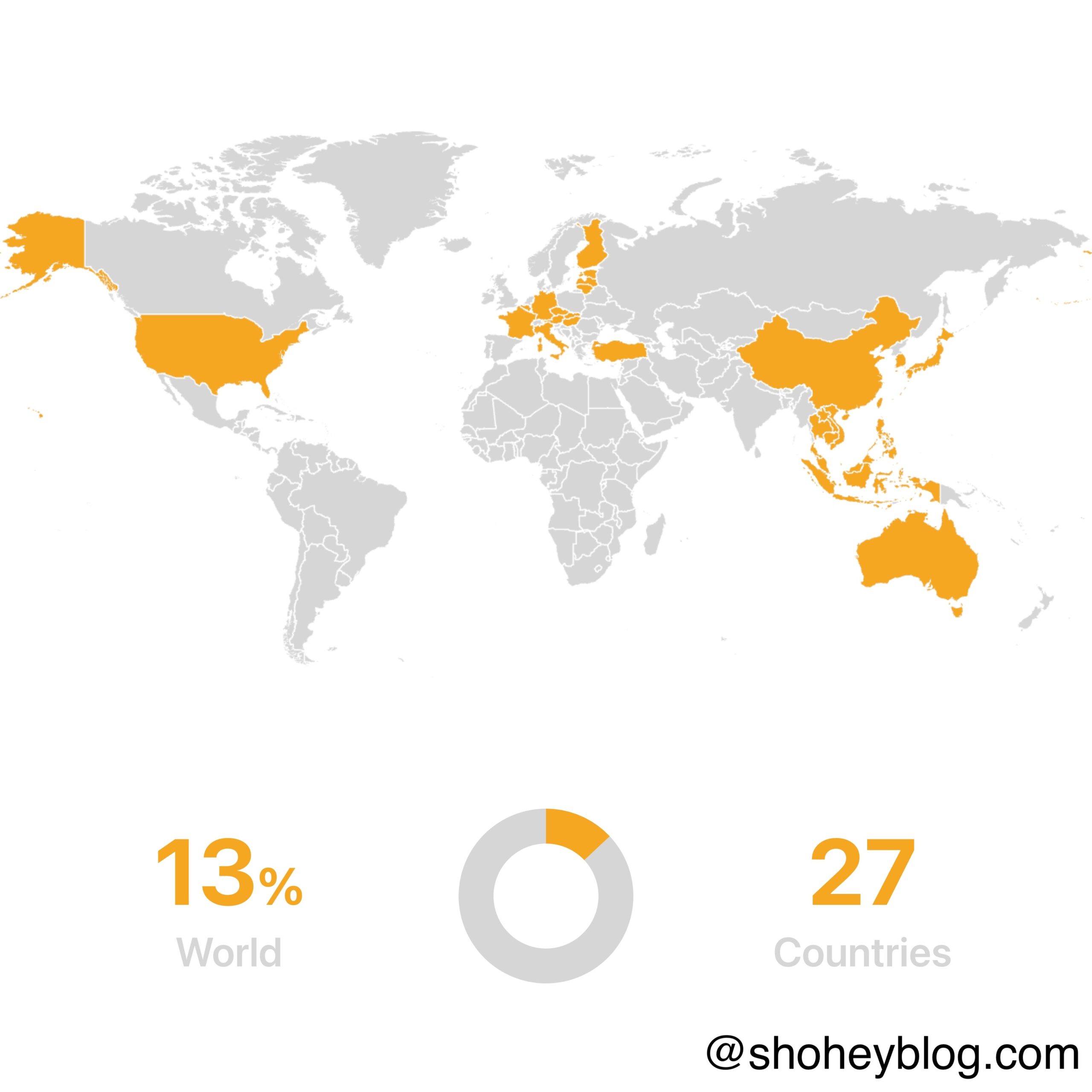2025年参議院選挙、投票した備忘録

この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。
2025年(令和7年)7月20日(日)、参議院選挙の投票日です。もちろん投票してきましたよ。20歳当時で選挙権を得てから自分が投票した人や政党が選ばれることはほとんどありませんでしたが、今回は、東京選挙区でも比例代表でも僕の投票先が選ばれました!わ〜い!すごく嬉しいです。
嬉しいは嬉しい結果となった今回の参議院選挙ですが、選挙前は相変わらずいろいろと騒ぎが起きますね。東京都に暮らす一人の有権者である自分の備忘録としてまとめます。
僕の国政のスタンス
素人な考えではありますが、住んでいる市区町村や都道府県ではなく「国」へ期待すること・思うことは大きく3つです。
- 国へ払う税金は少なめ
- 外交と防衛の行動力が高め
- これらを実施する人は65歳未満
国税は少なめに
ばら撒くほどの税金があるなら最初から取るな、です。
外交と防衛に注力
地域のことは地域で対応できれば理想的です(まあ、現実問題、市民に一番近い市役所は国がやることも東京都がやることも市がやることもなんでも一次受付窓口みたいに便利屋状態にさせられているけども…)。国としてやることは「国」単位のことに集中してほしい。なので外交と防衛の対応力には長けていてほしいです。
体力と見た目が良い人
(今回は参議院議員さんを選ぶ選挙ではありましたが)政治活動の場で、認知症になっていそうな人に僕らの代表として活動してもらいたいと思いますか?65歳以上になる人はそもそも議員になれないようにしてほしいです。介護されているようなヨボヨボの見た目、ひどく腹がでた体型、ダサいスーツの着こなし。やることも見た目もパッとしない政治家には引退してもらわないと。
やったこと・思ったこと
ボールペンで書いてみた
「投票用紙に鉛筆で書かせるのは、改ざんするためだー!」
といった投稿が投票日前にインターネット上で流れていました。不正防止のために鉛筆ではなくボールペンで書くべきだ!といった論調ですね。では論(?)より証拠!ネットで情報を得ることに偏りがちな現代人の自覚は僕自身にもあります。なら試してみよう!ということで、自宅で使用しているボールペンで投票用紙に書いてみました。使用したボールペンは、無印良品のボールペンです。

にじむことも、かすれることもありませんでした。全く問題なく解読可能な文字で投票しました(水性ボールペンは消えちゃうようなので、使わないようにしてください)。この確認のためだけに写真や動画での撮影はしていません。なので、証拠書類は掲載できません。僕のこの発信内容を信じるか信じないかはお任せします。ちなみに、投票用紙はユポという合成紙で、折っても開きやすいので開票作業がしやすくなるようです。
選挙の投票用紙は、合成紙「ユポ」に印刷などの加工を施して製造されています。ユポとは、株式会社ユポ・コーポレーションの独自製法によって製造された、フィルム法合成紙です。(後略)
「不正のために鉛筆で書かせているんだ!!」と憶測が飛び交うのは、一部の国民にそう思わせてしまうほど今までの日本の政治が信用されていない証拠ですね(もしくは何がなんでもケチをつけたいだけの輩)。僕自身は持参したボールペンで投票用紙に初めて書きましたが、感想としては、
「鉛筆でもボールペンでも自分が納得するならどっちで書いても良いんじゃね?」
です。これは、各個人で判断して各個人がやれば良いだけのことです。むしろ、投票所で本人確認を全くしないことの方が大問題だと思っています。
本人確認は必要では?
日本政府、省庁は明らかにマイナンバーカードを作ることを推奨していると思われます。この記事を書いている2025年7月時点で約80%の人がカードをすでに保有しています※1。なら、この「顔写真付き本人確認書類」を使って投票のときに本人確認をするべきです。
投票用紙だけを持っていけばそのまま投票ができちゃうのが現状です。「投票用紙を持っている = 本人」という扱いはザル過ぎます。ガバガバです。ガバナンスがガバガバなんす。それとも、本人確認という作業を増やしたくない思惑でもあるのか〜い??? ←効果的な本人確認がされていないという「事実」に対して、こういう「解釈」をすると陰謀論につながるわけですね。
メモメモ_φ(・_・
これは選挙ルールを管理している人たちに改善してもらいたいです。
テレビはもう不要だな
現役世代でテレビ番組を敢えて見たいと思う人は少なくなってきているのではないでしょうか。「テレビ番組を見たい」ではなく、「大きい画面で見たい」が本当の欲しいものですよね?テレビ局が作ったニュースははじめからシナリオありきの偏向報道なので、公平性なんてありません。僕が心がけているのは以下の2つです。
- インターネットで調べる
- 自分で見に行く・聞きに行く
大手メディアでも個人でも「切り抜き動画」のような前後の文脈を掲載しないで一部分の発言や情報だけであーだこーだ偏った発信をする人が多いですよね。本当の公平性を保つなら、動画などは編集せずに全て掲載すればいいんですよ。また、引用元を掲載しない発信は信用ゼロです。常に「ソース(情報源)は?」の頭が必要です。あとは自分の目で見る・自分の耳で聞きに行く。そして、自分で決める。ボールペンで投票用紙に書いたのも実際に自分の目で確かめたかったからです。
面倒に思う気持ちはわかりますよ。切り抜き動画なら30秒程度でなんとなくまとまっている感じがしますよね。都合よく切り抜きされているからこそ、僕らの脳みそは心地よく見ることができるんだと思います。嘘情報でも見やすいものを信じやすくなっちゃいますよね。
選挙前に党首討論が活発になりますが、1時間を超える討論をず〜〜〜〜っと見るだけ聞くだけって飽きちゃいます…。でも、見てみないとわからないこともあります。
例えば、Aという政策を推す党や党首がどのように説明しているかを生で聞けるのは貴重です。グダグダネチネチとした話し方で内容が空っぽな人もいます。あれ?結局それ質問の答えになってなくね?などもあります。伝わらなきゃ意味がない。こういうことは、文書やポスターを見ただけではわからないことです。政党別にどの政策に賛成か反対かといったマルバツ一覧表も見かけますが、あれは大雑把な違いを知るための道具としては便利です。深く知るならその人間の喋りを見るのが大事です。
これも、各個人でやれば良いことです。すぐにできることです。他人や制度を変えずともできます。
僕のこのブログも引用元のURLを載せて発信を続けます。
東京選挙区の7人
東京都では有権者数が約1,100万人、そのうちの約61%(およそ705万人)が投票しました。東京から参議院議員に選ばれた7人は下の表の通りです。
| 名前 | 所属 | 年齢 | 票数 |
|---|---|---|---|
| 鈴木 大地 | 自民 | 58 | 約77万 |
| さや | 参政 | 43 | 約66万 |
| 牛田 茉友 | 国民 | 40 | 約63万 |
| 川村 雄大 | 公明 | 41 | 約60万 |
| 奥村 祥大 | 国民 | 31 | 約58万 |
| 吉良 佳子 | 共産 | 42 | 約56万 |
| 塩村 文夏 | 立民 | 47 | 約51万 |
参照:NHK、東京都選挙管理委員会
いやぁ、これだけ自民党のダメっぷりが話題になっていたのになんで鈴木大地さんが1位なんでしょうか…。NHKの全国開票マップを見ると、市区町村ごとにどの候補者に何票入ったかを見ることができます。とてもわかりやすいです(NHKはこういうときに使うものですね笑)。マップを見ると、東京都はまあまあ赤いです(=自民党の鈴木大地さんが1位ということ)。

参照:NHK 全国開票マップ
さらに、自民党と手を組んでいる公明党は桃色です。その公明党の川村雄大さんが1位当選しているのが、
23区
- 足立区
- 荒川区
- 江戸川区
- 葛飾区
- 北区
市部
- 八王子市
- 東村山市
- 東大和市
- 武蔵村山市
- 瑞穂町
島しょ部
- 八丈町
でした。なんでなの…。
この結果は、東京で暮らすときにどんな住民が多い街なのかを考える判断材料にしてみてくださいね。
投票しなかった人へ
どの候補者も政党もいいと思わなかった。誰に投票したらいいかわからない。だから、投票しなかった。そういう人たちの声、ちらほら聞きます。僕個人の感想ですが、そんな人たちに対して思うことがあります。
ダサいです。
「誰に投票したらいいかわからない」と思ったなら、その気持ちを投票用紙に書けばよかったじゃん。大きくバツ印を書いて投票すればよかったじゃん。やらない言い訳ばかりで。うん、やっぱりダサいです。あなたは自分で自分の思いを伝える機会(投票)を自分で放棄したんですからね。
無駄遣い削減、増やすのは?
今の日本で話題になるのは、税の「使い方」が多いです。税金の無駄遣いを見直した後は、僕らが日本で働き、稼いで、持続可能な社会の一端を担うわけですが、今までと同じ働き方で十分なのでしょうか。議員の人数なんて今の半分近くに減らして、外国のスパイじゃないことを確かめれば良しとして、その後ですよ。諸外国から日本にお金が流れ込んでくる産業や仕組みが必要な気がしますが、ご意見やアイデアはありますか?
まとめ:2025参議院選挙
2025年の参議院選挙の備忘録としていろいろ書きました。今回はなんだか新旧対決のような構図にさせられましたね。既存政党 vs 新興政党、オールドメディア vs ネット。日本国内で分断している場合ではないのですが、僕ら有権者を分断させるようなことをしてきたのが今までの日本政治な訳ですからねえ。今までの政治の舵取りをしてきたのって誰だっけ?それを都合のいいように情報発信をしていたのは誰だっけ?
今回は投票が終わっただけなので、次は、選ばれた人たちの活動をチェックしていきましょう。インターネット上での切り抜き動画が溢れている時代だからこそ、「できる限り情報源・引用元を調べること(オンライン)」と「自分で見聞きすること(オフライン)」の2つを忘れたくないものです。